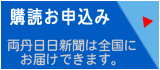両丹日日新聞2014年7月20日のニュース
 引き揚げ:仲間がバタバタ死んだ−強制労働耐えた平野力さん
引き揚げ:仲間がバタバタ死んだ−強制労働耐えた平野力さん
 世界記憶遺産への登録を目指すシベリア抑留と引き揚げの資料。引き揚げは舞鶴だけのことではなく、日本全国にかかわりがある。福知山市にも多くのシベリア抑留者が帰郷してきた。半田の獣医師、平野力さん(90)も、その一人。体験してきたことを問うと、「仲間がバタバタと死んでいった。そりゃあ、みじめなものでしたよ」と、静かに語り出した。
世界記憶遺産への登録を目指すシベリア抑留と引き揚げの資料。引き揚げは舞鶴だけのことではなく、日本全国にかかわりがある。福知山市にも多くのシベリア抑留者が帰郷してきた。半田の獣医師、平野力さん(90)も、その一人。体験してきたことを問うと、「仲間がバタバタと死んでいった。そりゃあ、みじめなものでしたよ」と、静かに語り出した。
■「ダモイ、ダモイ」にだまされ 貨車はシベリアへ向かった■
市内拝師の生まれ。現在の岐阜大で学んで獣医師になり、昭和19年10月1日に弘前の連隊へ入隊。10日ほどで大陸へ渡った。関東軍に着任した頃には、南洋で玉砕、撤退が続き、人も物資もどんどん南方へと移していた。満州に残っている部隊は「鉄砲の撃ち方も知らない者ばかりになっていました」。開拓団などから「根こそぎ動員」で現地召集された人たちで補充していたからで、敗戦、武装解除を経てソ連軍の指揮下に入り、シベリアへ移送された日本兵の中には、こうした「つい先日まで開拓民」だった人も多かったという。
移送は貨車。家畜か荷物のように詰め込まれて満州を後にした。「ダモイ(帰る)、ダモイ。トーキョー・ダモイ」とソ連兵がしきりに言う。「日本へ帰れる」と喜んだ者もいたが、平野さんは「そんなに甘くないはず」と身構えていた。懸念の通り、列車はどんどん北へ向かい、シベリアの荒野へと連れて行かれた。
「日本海だ、やっぱり帰れるんだ!」と喜んだ者もいたバイカル湖を過ぎ、シベリア鉄道は延々走る。まだ10月になったばかりというのに、外は零下で車内は震えるほど寒い。途中で止まるたび、ソ連兵が「トケイ、トケイ」と時計を奪っていく。抵抗できるわけもなく、されるがまま。これから自分たちがどうされるのか分からない恐怖。
「戦争でヘトヘトになっていたところへ、抑留でしょ。敗戦で心の支柱が無くなり、これから先の不安ばかり。食べる物もなく、みんな無力感でいっぱいでした」
■バラックの収容所 わずかな黒パン分けあい■
 送り込まれたラーゲリ(収容所)は馬小屋と同じ粗末なバラックだった。寝床は2段になっていて、凍える夜にも毛布が一人に、ただ1枚。周囲には電気を流した鉄線が張り巡らされ、見張り台からは絶えず自動小銃が見下ろしている。「逃げれば撃たれても文句を言えんということです」
送り込まれたラーゲリ(収容所)は馬小屋と同じ粗末なバラックだった。寝床は2段になっていて、凍える夜にも毛布が一人に、ただ1枚。周囲には電気を流した鉄線が張り巡らされ、見張り台からは絶えず自動小銃が見下ろしている。「逃げれば撃たれても文句を言えんということです」
食べ物といえば、日本人にはなじみのない黒パンぐらい。それも「ソ連兵や上のもん(将校ら)が順にピンハネするから、わたしら兵隊のとこには、わずかしか来ない」。幹部候補生の試験を受け、見習士官で終戦を迎えた平野さんだが、収容所では一般兵扱い。わずかなパン、そして「野菜クズがほんの少し浮いた、顔が写るぐらい透明な」スープをみんなと分け合った。
■凍る大地と厳しいノルマ■
労働は過酷だった。大地は凍って、ツルハシさえはじき返す。「まるで鉄板に穴を掘るようでした」。それでもノルマは厳しく、「ブストライ(早く)、ブストライ!」「ラボート!(働け)」と監視兵にわめき散らされる。酷寒の中とあって、何度も凍傷になりかけ、仲間と指や鼻をマッサージしあった。
 水が無いので風呂に入れない。顔や歯も洗えない。シラミと南京虫ばかりわいて血を吸っていく。空腹と疲れで、倒れ込むように寝床についても、かゆくてたまらず、眠りが浅くなる。みんなどんどん体が弱り、死んでいった。「年寄りやないんですで。若い、体力旺盛やったもんが、そうやって次々死んでいくんです」
水が無いので風呂に入れない。顔や歯も洗えない。シラミと南京虫ばかりわいて血を吸っていく。空腹と疲れで、倒れ込むように寝床についても、かゆくてたまらず、眠りが浅くなる。みんなどんどん体が弱り、死んでいった。「年寄りやないんですで。若い、体力旺盛やったもんが、そうやって次々死んでいくんです」
寝ても起きても頭の中は食べ物のこと。とにかく空腹だった。半世紀以上を経た今も、当時のことは頭から離れない。「宴会やらで、食べきれずにどうしても料理が残りますわなあ。それを見ると、あー、これがあったら、あいつは死なんですんだのに、とねえ」。自身の苦難は気丈に語ってくれる平野さんも、仲間の死については、涙無しには語れなかった。
■帰りを待つ家族も必死−無数の岸壁の母たち■
日本人が抑留されている間、帰国を待つ家族らも、じっとしていたわけではなかった。引揚船が入港するたび、舞鶴には「もしやこの船に」と岸壁の母、岸壁の妻が詰めかけた。
平野さんの母は「わが子が寒い思いをしてるのに」と冬でも衣一枚で過ごした。父は病の体をおして、GHQや日本政府へ働きかける全国運動に参加。こうした人びとの「肉親を返せ」との声が大きなうねりとなって、抑留者の帰国がかなう日が来た。
収容所内で「帰国が始まるらしい」とのうわさを耳にしても、まだ信用しきれなかったが、日本人を大勢乗せた列車が東へ向かうのを見るようになると「今度は本当だ」と希望がわき、やがて自分たちの番が来た。ウラジオストックから乗り込んだ引揚船の名は「第一大拓丸」。いろんなことがありすぎ、最後まで安心できなかった抑留・引き揚げだったが、舞鶴が近づき、青い松が見えたとき「ああ、やっと帰って来たと思えました」。
夢にまで見たわが家へ帰宅。そこで母から知らされたのは、平野さんの名を呼びながら3カ月前に父が亡くなったとこと。「親父の死に目には間に合わなんだけど、私は帰ってこられただけ幸せ。シベリアだけじゃない、同級生の多くが南方で、沖縄で、特攻や玉砕してます。絶えてしもた家が近所にも、ようけあります。わしらのようなことは二度と若者に経験させたらいかん。戦争は絶対にいかんのです」
写真上=弘前からずっと行動を共にしてきた水筒、飯ごうを手に抑留体験を語る平野さん
写真中=舞鶴引揚記念館所蔵のラーゲリ(収容所)模型。見張り台と銃が日本人抑留者たちの自由を奪った
写真下=収容所の内部を再現した展示。すり切れた衣服、すすけた顔の抑留者たちが黒パンを分け合う。不公平の無いよう棒秤(ぼうばかり)を使って分けた(舞鶴引揚記念館)
[PR]
株式会社両丹日日新聞社 〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町1-99 TEL0773-22-2688 FAX0773-22-3232
著作権
このホームページに使用している記事、写真、図版はすべて株式会社両丹日日新聞社、もしくは情報提供者が著作権を有しています。
全部または一部を原文もしくは加工して利用される場合は、商用、非商用の別、また媒体を問わず、必ず事前に両丹日日新聞社へご連絡下さい。